i2i-Labo 荻野 瑠星

先進の計算科学を追求する
若手でもチャレンジできる自由な風土が、入社の決め手に
学生時代は、「心筋梗塞時におけるpH感知性GPCRの役割解析」という研究テーマに取り組んでいました。研究の中で最も印象に残っているのが、あるpH感知性GPCRに対する抗体作製です。前任者が失敗した状態で引き継ぐこととなり、そのマウスの抗体価を上げることに非常に苦労しました。前任者と同じ方法では難しいはず。そう考えた私は、様々な論文を調べる所から着手。最終的に研究室では前例がないアプローチを取ることで、目的の抗体価を上げることに成功したのです。新しいアプローチへの挑戦とその検証を繰り返し、ひとつの成果を目指す一連の研究プロセスは、私に研究の面白さを強く実感させてくれました。
その後、博士課程に進むべきか大いに迷いました。しかし、「研究の成果を直接社会に役立てたい」「役立つ場面に立ち会いたい」と、製薬に関わる企業での創薬研究の道を選択。JTに興味を持ったのは、「First in class」の新薬を世界の患者様に届けるという理念を掲げている点でした。新しい機序の薬であれば、既存の医薬品との併用も想定され、より一層、患者様の健康につながると考えたからです。また、「若手でもチャレンジできる自由な風土」も魅力を感じたポイントのひとつ。新しいことに挑戦していきたい自分に合っていると感じられたことも入社の決め手になりました。

ミッションは、先端技術を駆使して効率的な分子設計を行うこと
私が所属するi2i-Laboは2023年4月に新設された研究所で、「計算科学」「化学」「生物」の3つのチームから構成されています。具体的には、コンピューターを用いて化合物のスクリーニングやデザインを実施する「計算科学」チーム、メディシナルケミストとしての知識や技術を活かして化合物をデザインし、実際に合成する「化学」チーム、そして、医薬品としての有用性を検証するため、合成された化合物の生物活性を評価する「生物」チームという3つが、1つの研究所の中に備わっています。つまり、i2i-Laboにおいては「Dry研究」と「Wet研究」の緊密な連携・融合による新薬候補化合物の早期創出を目指しているのです。
その中で私は、「計算科学」チームに所属しています。近年の低分子創薬研究では、人間の頭では処理しきれないほど膨大な情報をもとにした化合物探索が欠かせません。そのような中で重要課題となっているのが、いかに効率的な分子設計を行うかという点です。JTでは、社外ツールの利用のみならず、量子力学やAIなどの融合技術の自社開発にも注力。化合物やタンパク質に関する膨大な情報を用いて、そうした技術をバーチャルスクリーニングや分子シミュレーションなどに実装することで、効果的かつ効率的な候補化合物の発生・提案に取り組んでいます。
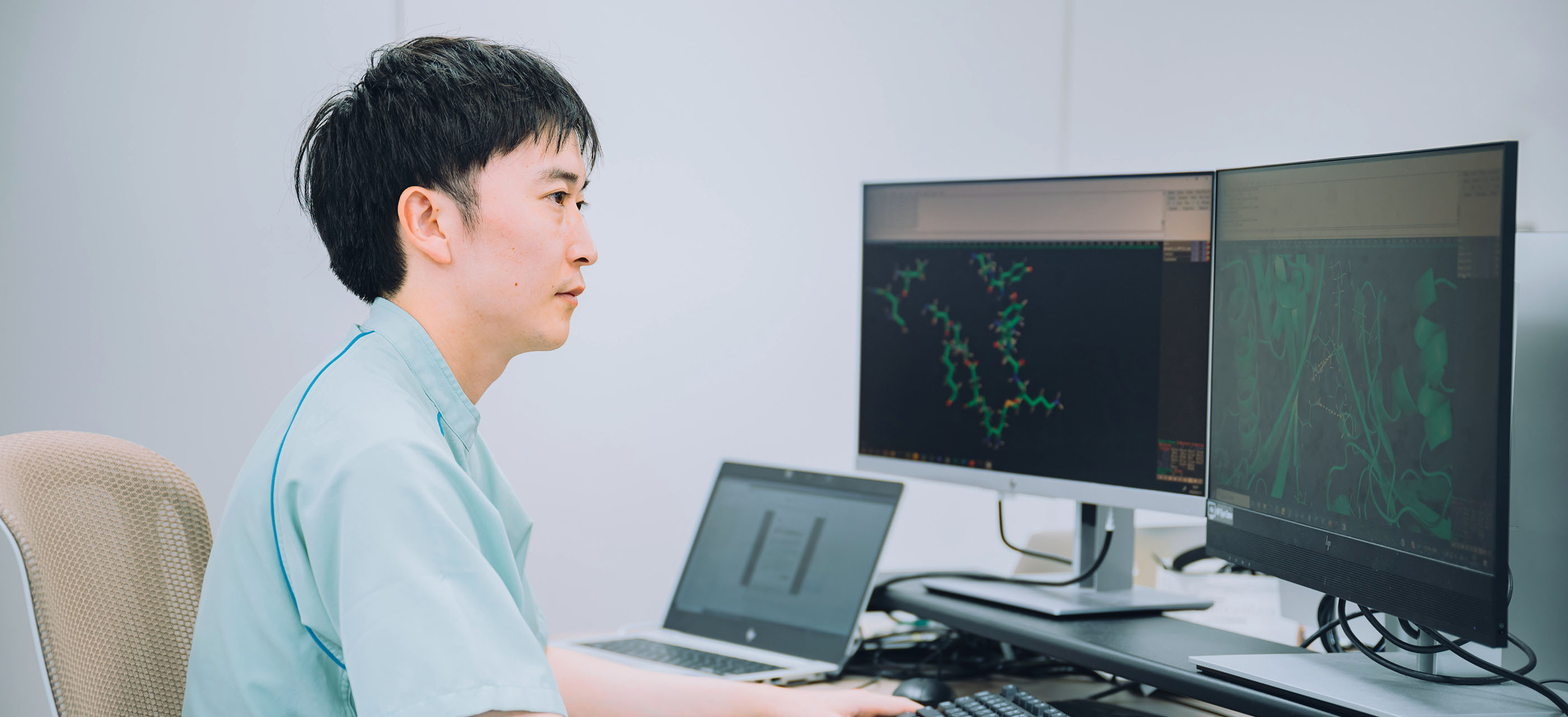
高度なシミュレーションで、
タンパク質複合体形成時の新規ポケットを発見
現在、私が取り組んでいるテーマは分子シミュレーションの観点から、「タンパク質の複合体化を化合物で制御する」ことがコンセプトです。一般的にタンパク質は単量体でも働きますが、一方で、多くのタンパク質は複合体を形成することで機能することも知られています。複合体の形成パターンは無限に考えることができ、その複合体の変化を計算科学によりシミュレーションするには、非常に大きな計算コストがかかります。
このような背景のもと、私は独自に複合体形成の評価軸を設定し、効率的に複合体の変化をシミュレーションするための技術を構築しました。そして、シミュレーションした複合体の中から、複合体を形成した時に現れる世の中でも報告例のないポケットを見出しました。現在、この新規ポケットに対して作用する化合物のデザインを「計算科学」チームの研究者と協力しながら実施中です。そして、デザインされた化合物については、「化学」「生物」チームとの連携を通じて、実際に合成され、コンセプト確認のための生物活性評価に進んでいます。
私のように新しい分野にチャレンジした経験を持つ人も多く、多様性が結集し、お互いの成長を支え合う職場の雰囲気もJTならではの魅力のひとつ。私自身、このような新たな挑戦を通じて、日々やりがいと成長を感じています。

魅力的な候補化合物を提案できるDry研究者となり、
新薬を世の中に送り出したい
JTは自社内に高性能コンピューターシステムを保有しており、従来技術の枠を超えて、量子力学やAIなどの融合による革新的創薬技術の開発・実装に取り組んでいます。AI/IT技術を取得できる素晴らしい教育システム・学習サポートも完備されていますし、自由度高く、新たな技術開発のスキルを磨ける点も、ここで働く大きな魅力です。
また私の場合、入社1年目に細胞や動物を用いた研究(Wet研究)に従事した後、現在手掛けている分子シミュレーションという「計算科学」の業務(Dry研究)に挑戦しました。この経験を通して実感したのが、Dry研究とWet研究のサイクルを繰り返し、互いに連携して結果をフィードバックすることが、洗練された候補化合物の早期創出を生むということです。
だからこそ今後はまず、このような連携を加速し、魅力的な候補化合物を提案できるDry研究者を目指したいと思っています。そしていつの日か、自ら習得したDry技術を用い、自身が設計・提案した化合物を新薬として世の中に送り出すことが、私の将来の目標です。
JTでは、「チャレンジする」という価値観が共有されており、主体的な取り組みが賞賛されます。若手でも自分の言葉で意見を表明できれば、新しい分野にも挑戦でき、やりがいに満ちた職場です。挑戦することに臆せず、困難を楽しみながら研究できる方、ぜひ同じ職場で新しい創薬研究をしませんか。
SCHEDULE
- 8:45出社。メールチェックとスケジュール確認。終夜計算の結果確認。計算条件の再設定。
- 10:00分子シミュレーション用のコード作成。
- 12:00昼食。
- 13:00コードのバグ修正。テスト計算。テーマについてメンバー間で進捗状況報告。
- 17:00データ整理。資料作成。
- 18:00退社。



