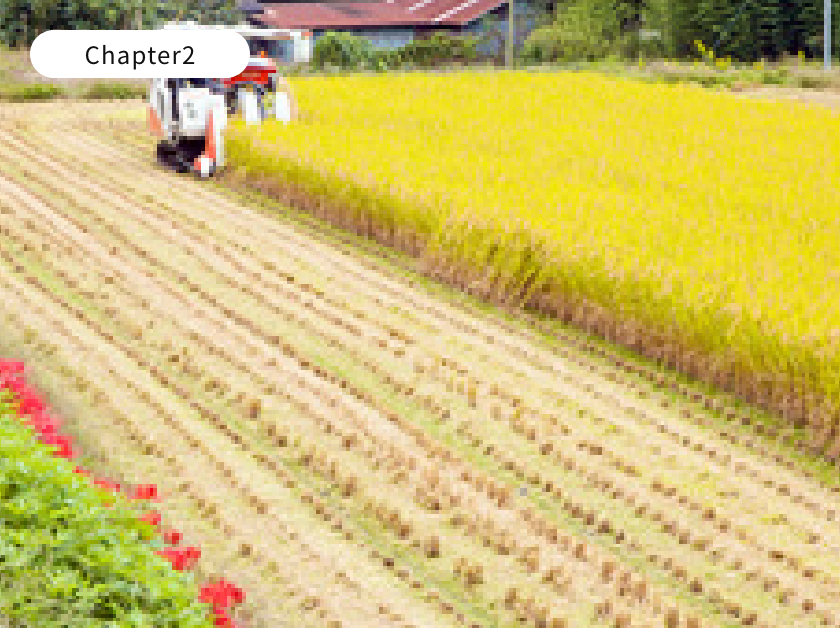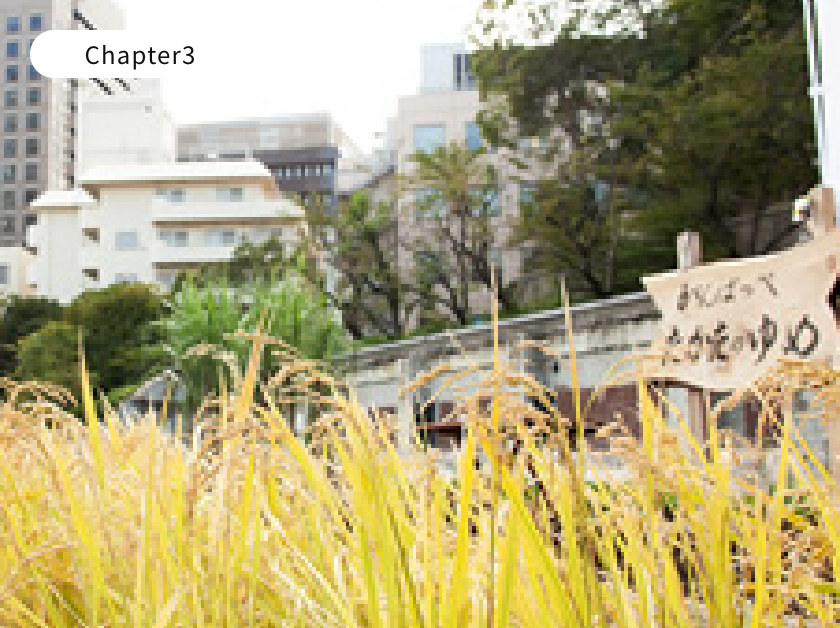Chapter2:現れた、たった一人の協力者

東日本大震災による津波の爪痕は深く、陸前高田市の多くの田んぼは被災田となります。市内の農家では、米づくりに適した土づくりを急ピッチで進めていきました。そうした中、復興支援米として選ばれた「いわた13号」でしたが、栽培する農家はなかなか現れませんでした。
苦労の末に初の栽培農家が誕生

「いわた13号」の栽培農家第1号となった、金野千尋さん。

見事に育った「たかたのゆめ」の刈り入れの様子。
事が大きく動き始めたのは、東日本大震災の発生から半年後の2011年9月。
東北でのボランティア活動を熱心に行っていたJT植物イノベーションセンターの研究員は、陸前高田市の復興支援として、第一次産業において何かできないか、と考えました。そして、貯蔵庫にある品種登録を取り下げた稲の種子は、まだ世に出ていない新品種であり、価値があるという想いに至ります。
それから2カ月後。その想いは形となります。初年度は、農家が優良な種子で生産できるようにする「原種」の栽培。2年目からは一般の食用として「飯米」を一定量作ることを想定。そして、岩手県で栽培できる品種として「いわた13号」が選ばれます。240粒の「いわた13号」は、2011年12月に貯蔵庫から取り出され、栽培が始まりました。
JTの復興支援活動としても動き出した米栽培は、温室内での増殖から始まります。そして、2012年3月には、6グラムの種もみから約3キロを収穫。4月には、栽培した「原種」を手に、陸前高田市を訪問します。そして、栽培してもらう農家探しに全力を注いでいきました。
しかし、県の奨励品種に指定されていない米を栽培する農家は見つかりませんでした。全ての農家に断られ、諦めかけていたとき、その日訪問した農家の方が知り合いの農家に電話をかけてくれました。その相手が金野千尋さんでした。話を聞いた金野さんは、栽培を快諾。偶然、15アールの田んぼが空いていたことに加え、金野さんが“新しい取り組みにも非常に前向き”であったことが、初の栽培農家誕生につながりました。
JTでは育成支援のため、その後も陸前高田市を訪問。「復興支援を掲げる以上、その出口までをしっかりサポートしたい。種子だけを提供して終わりにはできない」との想いのもと、現地での活動や、全国へのPR活動サポートを行うなど、今後も支援を継続していきます。