 |
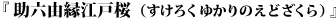 |

江戸時代の最大の歓楽地であった吉原を舞台に、主人公の助六と人気遊女の揚巻、金と権力を持つ老人の意休らはじめ、魅力的な人物が登場する人気作品です。ここで登場するキセルは、遊女たちが助六への愛情を表現する重要な小道具。男前できっぷがよい助六を何とか誘おうと、遊女たちが次々と助六へキセルを差し出すシーンが出てきます。このときの助六のセリフ「キセルの雨が降るようだ……」は、あまりにも有名。江戸時代では、キセルは男女の愛情をはかるバロメーターだったようです。 |
|

 |

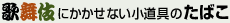  |
 |

朱羅宇キセルとたばこ盆
遊女たちが朱羅宇のキセルを愛用していたことから、歌舞伎の中にも、朱羅宇のキセルを手にした妖艶な遊女がしばしば登場します。ちなみにこのたばこ盆は、新吉原の扇屋で人気を博した遊女「花扇(はなおうぎ)」が使用したものといわれています。
 |
 |
|
 |

