 |
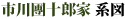   |

「荒事」の創始である、歌舞伎界屈指の名門。代々の團十郎は名優揃い。十二代目市川團十郎は、アメリカやヨーロッパなど、海外公演も多数行っていました。十一代目市川海老蔵は、大河ドラマをはじめ、TVや舞台の出演も多数。
 |
 |

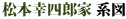   |

市川團十郎家とは親戚関係。名優も多数誕生しています。九代目松本幸四郎は、日本舞踊の松本流宗家で、七代目市川染五郎は松本流家元。2人とも、舞台やTVなどをはじめ、幅広い分野で活躍しています。 |
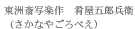 |
|
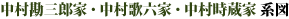   |

江戸歌舞伎の劇場を起こしたと言われる、元祖猿若勘三郎(初代中村勘三郎)を祖とする中村座の名跡。十八代目中村勘三郎(五代目中村勘九郎)はニューヨークや浅草などで芝居小屋を設営し公演を行うなど、幅広く活躍しました。
三代目中村時蔵を祖父に持つ二代目中村獅童は、映画やTVの出演も多数。
 |
   |

市川團十郎家と並び、約250年の歴史を持つ名門。七代目尾上菊五郎、五代目尾上菊之助ともに、女形や二枚目をはじめとするさまざまな役を演じ、「世話物」や「所作事」など、幅広い芸の領域を持っています。
 |
|