伝統ある喫煙具文化を伝えるために
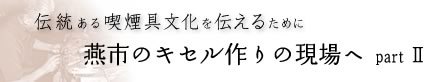 |
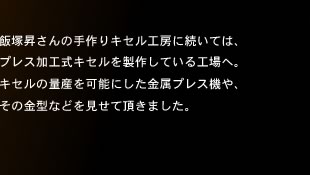 |
 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| そして、プレス加工式キセルを現在も作り続けている飯塚金属(株)も、全国で開かれる伝統工芸品の展示会などに出品するなど、キセル作りの息吹を後世に伝えるよう日々努力をしています。 かつてキセル生産日本一を誇った、新潟県・燕市。そこでは今でも、日本の喫煙文化の伝統を伝えるキセルが日々作られているのです。 |
|
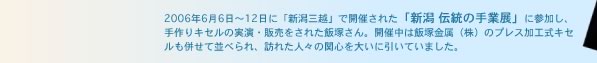 |
 |
| ※飯塚昇氏は、2025年1月28日に92歳で逝去されました。 |
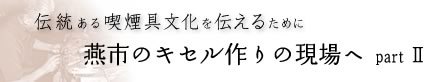 |
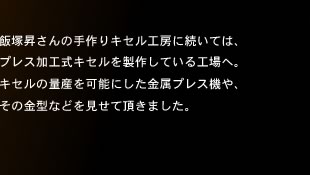 |
 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| そして、プレス加工式キセルを現在も作り続けている飯塚金属(株)も、全国で開かれる伝統工芸品の展示会などに出品するなど、キセル作りの息吹を後世に伝えるよう日々努力をしています。 かつてキセル生産日本一を誇った、新潟県・燕市。そこでは今でも、日本の喫煙文化の伝統を伝えるキセルが日々作られているのです。 |
|
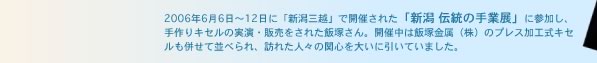 |
 |
| ※飯塚昇氏は、2025年1月28日に92歳で逝去されました。 |