煙管[キセル]
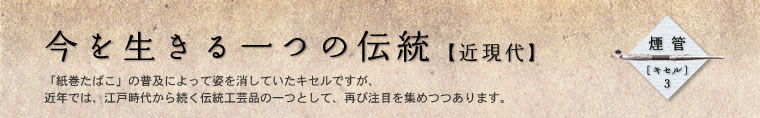 |
| 明治37(1904)年に施行された「煙草専売法」によって開始されたたばこの専売は、昭和60(1985)年まで続きました。この間、社会情勢は大きく変化し、たばこを取り巻く環境も変遷を遂げていったのです。 まず大正時代に入ると、都市部を中心に「紙巻たばこ」の需要が増え、人々の喫煙形態は“「細刻みたばこ」をキセルに詰めて吸う喫煙”から“「紙巻たばこ」での喫煙”に変化していきます。そして第2次世界大戦後には、ライフ・スタイルの変化に伴って個人の嗜好が多様化。さまざまな特徴を持つ「紙巻たばこ」の銘柄が多数作られるようになりました。 一方でキセルによる喫煙は激減し、日本で製造されている「細刻みたばこ」は一つの銘柄を残すのみとなったのです。 |

「専売当初のたばこパッケージ」 |
|||
| 「紙巻たばこ」の普及による喫煙形態の変化によって、大正時代以降には、キセルによる喫煙は減少していきます。そして第2次世界大戦後には、日本人の生活からキセルはほとんど姿を消し、主に伝統文化を継承する歌舞伎などの演出で、限定的に使用されるようになりました。 しかし、日本のキセルは新潟県燕市などの地域で、伝統工芸品の一つとして、昔かたぎな職人たちの手によって作られ続けてきました。これが近年では、その歴史や細工の美しさも相まって、再び人々の関心を集めつつあるのです。 >> 新潟県燕市でのキセル作りの情報はこちら |
|||||
| 時代劇や歌舞伎の舞台などでは、江戸時代の風俗を示すシーンにおいて、効果的な演出をする小道具の一つとしてキセルが用いられます。特に歌舞伎では、キセルの形状で持ち主の人柄を示すだけでなく、男女の愛情を表現する場面で利用されるなど、舞台演出における重要な役割を果たしているのです。 |
|||||
 |
「『横島田鹿の子の振袖』 |

「銀・銅・四分一手綱形きせる(19.8cm)」 |
|||
| 近年になると、キセルが育んできた歴史や文化などに魅せられる者も現れ、細工や意匠の美しいキセルなどが求められるようになります。やがてこのキセル熱は、ゆっくりとしたペースで人々の間に浸透。現在では、伝統を受け継ぎながらも、現代人の嗜好に対応したキセルが作られるようになっています。
|
||||

「SHIEN」(「日本たばこアイメックス」提供) |

「福一煙管 彩」(「kagaya新宿店」提供) |
|||
「小錦二ツ銀」(「日本たばこアイメックス」提供) |
「浅草煙管登り龍五寸」(「柘製作所」提供) |
|||
|
||||||||||||||||||



