役者絵
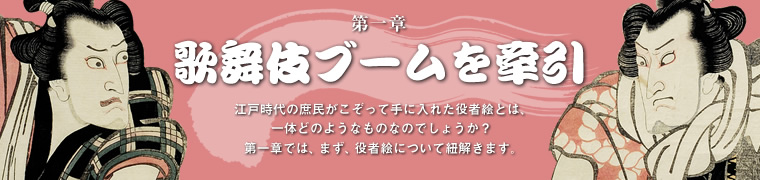 |
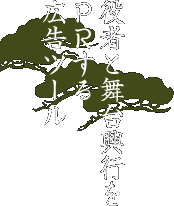 |
歌舞伎が庶民の娯楽として注目を浴びた江戸時代には、人気の高まりに呼応するように、役者たちの動向にも注目が集まります。やがて、彼らのファッションを真似する人が現れるなど、役者たちは庶民にさまざまな影響を与えるようになりました。このため、当時の人々の娯楽として華開いた浮世絵にも役者の姿が描かれるようになり、“役者絵”という一つのジャンルが確立されたのです。 役者絵に描かれたのは、当時の人気役者たちの舞台での姿をはじめ、楽屋での様子や日常の姿などであり、役者絵とは、現代でいう「ブロマイド」のような存在でした。一方で、舞台の一場面を描いた芝居絵は、役者絵の中でも芝居の興行を知らせる「チラシ」のような役割を果たしていました。 こうした役者絵の流行とあいまって、この分野で特に名を馳せる絵師も多数現れました。なかでも“歌川派”は揺るぎ無い地位を築き、その一派の一人である歌川豊国(とよくに)は、一世を風靡しました。 |

『廓文章(くるわぶんしょう)』/文化11(1814)年/歌川豊国画 |
| 江戸時代の歌舞伎の中心地は江戸と上方(=京都・大坂)でした。そのため役者絵も江戸と上方の両地で制作され、東西それぞれで活躍する絵師たちが、それぞれの地域の人気役者を生き生きと描いていきました。 一方で、役者たちの東西交流も行われ、江戸の演目が上方で上演されたり、上方の演目が江戸で上演されたりしたほか、江戸と上方の人気役者が共演する興行が打たれることもありました。この結果、役者絵の世界でも江戸と上方で同じ演目や同じ役者を描いた絵が生まれるようになります。その一例が下の2枚の絵です。 文化11(1814)年に描かれた江戸の役者絵『双蝶々曲輪日記』には、江戸に招かれた上方の人気役者・3代目 中村歌右衛門が、江戸の人気役者である3代目 坂東三津五郎と共演したシーンが描かれています。そして、その7年後の文政4(1821)年に描かれた上方の役者絵『散書廓文章』には、上方に上った三津五郎が、歌右衛門と、再び共演したシーンが描かれています。舞台の細部までを色鮮やかに表現している江戸の役者絵と、背景を抜きにして、役者に焦点を当てた上方絵。この2作は、両者の違いが浮き彫りとなった作品といえるでしょう。 |
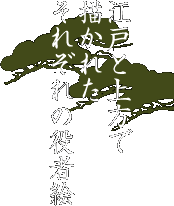 |
 |
 |
『双蝶々曲輪日記 |
 |
 |
『散書廓文章(ちらしがきくるわぶんしょう)』 |