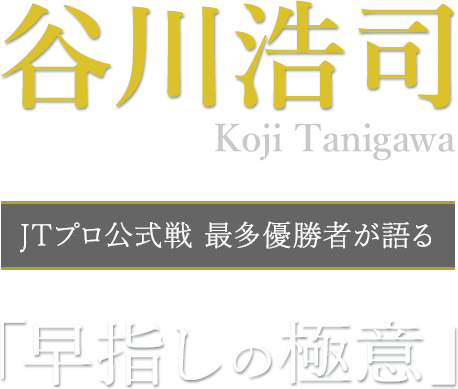谷川浩司九段インタビュー
Sports Graphic Number1018号
(2021年1月7日発売)に掲載
14歳でプロデビューして7年で棋界の頂点を極めた史上最年少名人は、持ち時間10分の早指し戦でも強さを発揮した。事前の戦法予測と攻めの勢いでいかに自分のペースに持ち込むか。41年の歴史を誇るJTプロ公式戦、最多優勝者にその極意を聞いた。
片山良三=文
text by Ryozo Katayama
和多田アヤ=写真
photographs by Aya Watada
5歳のとき、兄弟喧嘩を鎮めるためにと父から盤駒を買い与えられた谷川浩司少年は、5つ年上の兄と百科事典の将棋のページを奪い合いながら駒の動かし方を覚えた。現在の優雅な立ち振る舞いからは想像もつかないが、負けず嫌いが度を越して、駒を噛んだり投げつけたりしたこともあったという。

photograph by Aya Watada
兄・俊昭さんも、のちにアマチュアの強豪として名を馳せたほどの人なので、はじめのころは負けてばかりだったのも仕方がない。それでも夢中になって続けられたのが将棋との相性。出会いは運命的なものだったに違いない。
11歳、小学5年という記録的な早さで奨励会に入り、14歳、中学2年で四段に昇段。加藤一二三以来、史上2人目の「中学生棋士」となった。本当の凄さはここからで、入り口のC級2組で1期だけ足踏みをさせられたものの、翌年からは4期連続の昇級昇段を続けてA級まで一気に駆け上がり、20歳の誕生日の寸前に八段になる。
棋界のベスト10が揃うA級でもいきなり7勝2敗の好成績をあげて名人への挑戦権を奪うと、翌年当時の加藤一二三名人を4勝2敗で破り、最高位である名人の高みに登りつめたのだ。ときに21歳2か月と9日。最年少名人の記録は、未だに破られていない。
以後、名人位を5期以上獲得することでしか得られない永世名人資格(引退後に十七世名人を襲名)に到達するなど、タイトル獲得は歴代4位の27期。タイトル戦以外の棋戦優勝も22回を数える。58歳になったいまも現役で、順位戦ではB級2組に在籍。今期は、名人への最年少記録更新の可能性を唯一人持っている藤井聡太二冠と、40歳差の激闘を演じた。

photograph by 将棋日本シリーズ総合事務局
「棋は対話、という言葉があります。対局中に言葉をかわすことはなくても、指し手をやり取りすること自体が対話。問いかけに耳をすませ、その言い分を聞いてあげたり、あげなかったりするのが将棋です。その繰り返しのうちに、お互いの考えが理解し合えるわけです。
私は39歳年長の大山先生(康晴十五世名人)と、重大な対局を通じて対話させていただき、逆の立場で40歳年下の藤井さんと指し手で対話しました。
囲碁の橋本宇太郎先生(本因坊などタイトル8期の名棋士。87歳で亡くなるまで現役を貫いた)の“100年をつなぐ”という考え方に感銘を受ける年齢となって、私も上下80年をつなげることができたのかなと思っているところです」
前期順位戦でB級1組からの陥落が決まったとき、ひょっとしたら引退してしまうのではないかと心配するファンの声も少なくなかったが、それをいい意味で裏切ってくれたのが谷川だった。
B級2組に上がってくる藤井聡太との対局を楽しみにしたのではないかという筆者の観測は大きく的を外していなかったようだが、その大一番に敗れたあとも、谷川がモチベーションを失っていない様子なのが少し意外で、そこもうれしく感じた。
「コロナ禍にも影響されて、しばらく休止していた研究会があったのですが、これを10月から2つ復活させました。持ち時間15分、切れたら60秒という早指しで、午前に1局、午後に2局指しています。

photograph by 将棋日本シリーズ総合事務局
感想戦もしっかりやることで、若い人の感覚に大いに刺激されています。斎藤 (慎太郎八段) さん、菅井(竜也八段)さんらに家に来てもらっていますが、彼らに見捨てられないように、必死に喰らいついて行くつもりです」
谷川が初めて手にしたタイトルは、1局を2日かけて戦う持ち時間各9時間の名人戦七番勝負だったが、その対極に位置する超早指しの棋戦でも無類の強さを見せた。
将棋日本シリーズJTプロ公式戦は公式戦としては最も短い持ち時間10分で、使い切ったら1手30秒以内という非常に忙しい設定。1分×5回の考慮時間はあるものの、一手ごとにじっくり読めるタイトル戦とは全く異質なステージと言っていい。しかし、この棋戦での最多優勝を誇るのも実は谷川だ。過去41回の大会で6回優勝、準優勝も5回という圧倒的な実績を残している。
「JTプロ公式戦が創設されたのは私が六段のときでした。超早指しの公式戦で、しかも公開対局という画期的な新棋戦がスタートしたわけですが、第1回は大山康晴、中原誠、米長邦雄、加藤一二三という、当時の将棋界の看板スター4人によるトーナメント。自分にはまだ遠い棋戦だなと思っていました。
それが第2回大会で出場枠が8人に広がり、第4回からは現在の12人に。私の初出場はその第4回で、A級八段に上がったことでベスト12の枠の中に入ることができました。'06年から獲得賞金上位者に出場権が与えられるようになりましたが、今も昔も、私はこの棋戦に出場する12人がトップ棋士だと思っています」
谷川の初優勝は'89年、第10回の記念大会だった。仙台市で行われた決勝戦は、初代竜王の座に就いた島朗と、名人と王位の二冠を保持していた谷川の激突。竜王戦が誕生し、名人とともに棋界の二大タイトルとして並び立った直後に、この頂上決戦が日本シリーズで実現したのだから大変な話題を呼んだのも当然。
このとき、島26歳、谷川27歳。ベテランのトップ棋士が多かった当時としては、若手同士の対決というフレッシュさも魅力的で、しかも地方のファンにとっては直に観戦できる数少ない機会とあって、開場前に長蛇の列ができ、一般のニュースにも取り上げられるほどだった。
「この棋戦ならではなのですが、対局前の間の取り方には慣れが必要なんです。例えば登場の仕方。舞台の袖から登場することもあれば、客席の後ろからお客様の間を通って舞台に上がるという形もありました。和服で舞台への階段を上がるというのはけっこう大変なんです。
また、登壇したあとに設定されているインタビューも実は関門の一つ。気の利いた受け答えができなかったときは、直後の対局に影響してしまいました。初優勝がかなう前に準優勝が3年連続であったのですが、惜しいというよりも、早指し戦は相性が良くないんじゃないかという悲観が上回っていました。
あのとき、仙台の大勢のファンの皆さんの前で初めて優勝することができて、ひとつ壁を越えることができた気がしたものです」