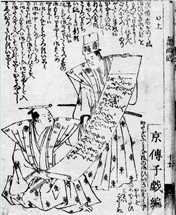「浮世絵」を読んでみよう!
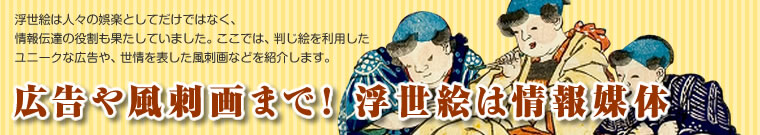 |
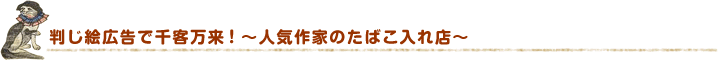 |
| 江戸時代に庶民の娯楽として人気を博した判じ絵は、やがて絵画というジャンルを超えて積極的に利用されるようになります。当時の人気作家であった山東京伝(さんとうきょうでん 1761〜1816)が、広告に判じ絵を利用したのもその一例です。 寛政5(1793)年にたばこ入れの販売店をオープンさせた京伝は、店を周知させるための広告を判じ絵で作成します。この広告は大きな話題となり、多くの人が彼の店の判じ絵を欲しました。また京伝は、判じ絵の広告を商品の包み紙にも利用。それを目当てに遠方からたばこ入れを買いに訪れた客も多く、店は大いに繁盛したということです。 |
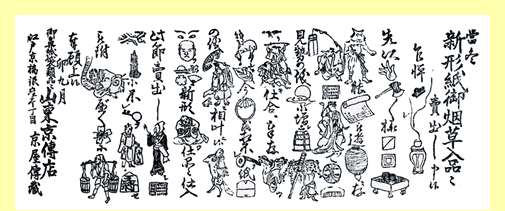 |
「京伝店判じ物仕立ての摺物(きょうでんみせはんじえしたてのすりもの)」 山東京伝がたばこ入れ店の売り出しを知らせるために作成した広告。『煙草展覧会図録』に掲載。 |
|
|
江戸時代後期の人気作家であった山東京伝は、作家として名をはせた一方で、絵師としても活躍した庶民を代表する文化人の一人でした。そんな京伝が、寛政5(1793)年に銀座にオープンさせたのが、「京屋」というたばこ入れの店です。 京伝は店の経営を父に任せ、自らは作家活動を続けつつ、店や商品の広告を自身が書いた作品に折り込んで店を盛り立てます。また、デザインにも携わり、珍しいデザインのたばこ入れを多数生み出したともいわれています。 「京屋」では開店当初、紙で作られたリーズナブルな“紙たばこ入れ”を中心に販売していましたが、次第に燻製の紙や革に似せた高級紙、さらには本物の革素材を用いた高価なたばこ入れまで扱うようになり、併せてキセルの小売りまで始めます。そして喫煙具以外にも、薬や京伝直筆の扇まで販売することで、「京屋」は大きな発展を遂げたのです。 |
||||||||||
 |
| 庶民が時代を謳歌し、面白おかしい浮世絵が流行した江戸時代も、次第に激動の時代=幕末へと推移していきます。外国からの脅威を受けたこの時代は、国内では反幕府運動を強める尊王攘夷派と幕府を支持する佐幕派が、勢力争いを繰り広げていました。 そうした世情が不安定な中で、人々は世の中の動きをしっかりと、そして冷静に見つめていました。このころ、出版された浮世絵では、直接的な表現を避け、役者や子どもを描き、その衣服や持ち物で、人物や関係諸藩をにおわせながら情勢を分析したり、ときには世情を皮肉ったりしています。浮世絵は江戸の地で作られたものが多く、幕府びいき、関東びいきになっているものが多いため、史実とは異なるところもありますが、当時の人々が幕末という時代をどのように見ていたかなどを知る手がかりとなっています。 |
 |
 「当振舞世直シ拳(あたりふるまいよなおしけん)」(画:国周/「たばこと塩の博物館」蔵) |
|
 「子供遊宝の当物(こどもあそびたからのあたりもの)」(「たばこと塩の博物館」蔵) |
 |
|