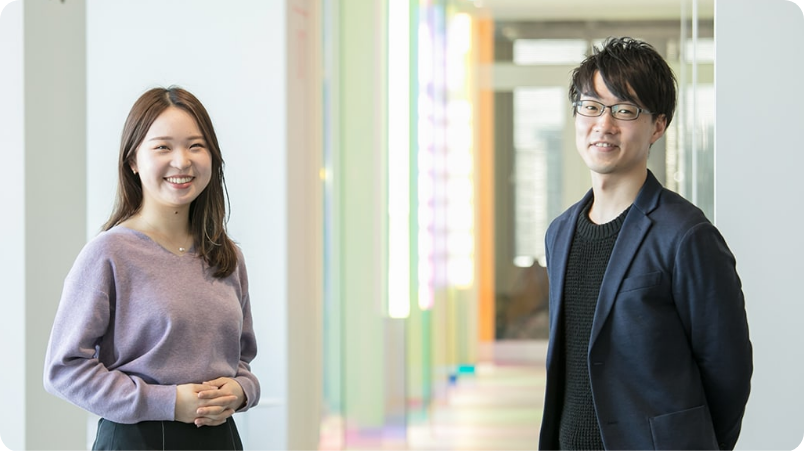-
 R&D部門とはGlobal Tobacco BusinessのR&D グループは世界中のメンバーと協業しながらOne Teamとして仕事をしています。バリューチェーンに占める割合は大きく、基礎的な研究から製品の仕様を決めるまでに必要なあらゆる業務・職種があることが特徴的です。
R&D部門とはGlobal Tobacco BusinessのR&D グループは世界中のメンバーと協業しながらOne Teamとして仕事をしています。バリューチェーンに占める割合は大きく、基礎的な研究から製品の仕様を決めるまでに必要なあらゆる業務・職種があることが特徴的です。 -
 基礎研究時代とニーズに応じた製品開発を支える技術の礎を創る
基礎研究時代とニーズに応じた製品開発を支える技術の礎を創る -
 技術開発研究成果を実用化できる技術へ
技術開発研究成果を実用化できる技術へ -
 製品開発技術を組合せコンセプトを実際にカタチにする製品化プロセス
製品開発技術を組合せコンセプトを実際にカタチにする製品化プロセス -
 製品評価たばこ製品の信頼性担保とリスク低減に関わる評価研究
製品評価たばこ製品の信頼性担保とリスク低減に関わる評価研究 -
 戦略策定R&Dグループの成果最大化とビジョン実現を目指して
戦略策定R&Dグループの成果最大化とビジョン実現を目指して -
 調達・品質管理RRP※デバイスの効果的なサプライチェーンを構築
調達・品質管理RRP※デバイスの効果的なサプライチェーンを構築 -
 研究開発支援現場を活かす研究開発を俯瞰した基盤づくり
研究開発支援現場を活かす研究開発を俯瞰した基盤づくり -
 山本 智裕人の心の豊かさを生み出すのは、創造力と、遊び心。まだ見ぬワクワクを届けていきたい。
山本 智裕人の心の豊かさを生み出すのは、創造力と、遊び心。まだ見ぬワクワクを届けていきたい。 -
 松本 理沙高度なリスク予測・評価の先に、「ひとのときを、想う」製品が生まれる。だからこそ、自分自身の限界を決めたくない。
松本 理沙高度なリスク予測・評価の先に、「ひとのときを、想う」製品が生まれる。だからこそ、自分自身の限界を決めたくない。 -
 片山 和彦研究全体を取りまとめ、テーマを見定める。クリエイティビティ溢れる環境で、最高傑作を生み出すために。
片山 和彦研究全体を取りまとめ、テーマを見定める。クリエイティビティ溢れる環境で、最高傑作を生み出すために。 -
 御園生 洋祐データサイエンスによる「香りのデジタル化」。新たな可能性に挑戦できる環境がある。
御園生 洋祐データサイエンスによる「香りのデジタル化」。新たな可能性に挑戦できる環境がある。 -
 太田 康介検証に基づく具体的かつ明確な指針を作ることで開発部門をサポートしていきたい。
太田 康介検証に基づく具体的かつ明確な指針を作ることで開発部門をサポートしていきたい。 -
 井上 貴詞社会やお客様の変化に柔軟に対応できる研究所に貢献していきたい。
井上 貴詞社会やお客様の変化に柔軟に対応できる研究所に貢献していきたい。 -
 小池 明子研究成果の効果的な蓄積と発進がメンバーの発想刺激に。世界の市場に繋ぐ、架け橋のような存在でありたい。
小池 明子研究成果の効果的な蓄積と発進がメンバーの発想刺激に。世界の市場に繋ぐ、架け橋のような存在でありたい。 -
 宇田川 久史自分の得意分野と好奇心を活かすことで仕事をたのしむことができる。
宇田川 久史自分の得意分野と好奇心を活かすことで仕事をたのしむことができる。 -
 清水 弥学んできたこと、経験してきたことだけにこだわらず、自分の価値や可能性を広げたい。
清水 弥学んできたこと、経験してきたことだけにこだわらず、自分の価値や可能性を広げたい。 -
 村越 克典誰も見たことがないたばこをより多くのお客様にお届けしたい。
村越 克典誰も見たことがないたばこをより多くのお客様にお届けしたい。 -
 大川 直記目に見えないものを可視できる数値解析。そこには無限の可能性がある。
大川 直記目に見えないものを可視できる数値解析。そこには無限の可能性がある。 -
 永山 萌夏たばこから広がる人の縁。コミュニケーションが大好きだから、たばこの開発をやりたかった。
永山 萌夏たばこから広がる人の縁。コミュニケーションが大好きだから、たばこの開発をやりたかった。 -
 桝田 雄気まだまだ新しいマーケットだからこそ、革新的な製品の開発に携わりたい。
桝田 雄気まだまだ新しいマーケットだからこそ、革新的な製品の開発に携わりたい。 -
 松葉 凌太新たな技術や製品を開発し続けることで、紙巻たばこにはない新しい価値の向上に貢献したい。
松葉 凌太新たな技術や製品を開発し続けることで、紙巻たばこにはない新しい価値の向上に貢献したい。 -
 浅野 有香里変わり続けるニーズにスピーディーに応え、新たなたばこ文化を創り出したい。
浅野 有香里変わり続けるニーズにスピーディーに応え、新たなたばこ文化を創り出したい。 -
 後藤 歩世界中のお客様に喜んでいただけるよう、時代の変化に対応しながら自分たちの知見を活かした提案をしていきたい。
後藤 歩世界中のお客様に喜んでいただけるよう、時代の変化に対応しながら自分たちの知見を活かした提案をしていきたい。 -
 長浜 徹いまだ「正解のない」発展途上の市場。お客様の生活を豊かにするために、これまでにないデバイスを開発していきたい。
長浜 徹いまだ「正解のない」発展途上の市場。お客様の生活を豊かにするために、これまでにないデバイスを開発していきたい。 -
 藤木 貴司多彩な専門分野を持つ仲間とアイデアを出し合い、これまでにない高付加価値なデバイスを作り出す。RRPデバイスの開発には夢がある。
藤木 貴司多彩な専門分野を持つ仲間とアイデアを出し合い、これまでにない高付加価値なデバイスを作り出す。RRPデバイスの開発には夢がある。 -
 涌井 浩伸困難な状況に対しても、前向きな姿勢で事業の成長、会社の成長を支えたい。
涌井 浩伸困難な状況に対しても、前向きな姿勢で事業の成長、会社の成長を支えたい。 -
 長田 悠加目的と意義を見極め、期待される以上の仕事していきたい。
長田 悠加目的と意義を見極め、期待される以上の仕事していきたい。 -
 木戸 祐一郎フェアネスを大切に、一人ひとりの力を束ねて、たばこの新領域を拓いていきたい。
木戸 祐一郎フェアネスを大切に、一人ひとりの力を束ねて、たばこの新領域を拓いていきたい。 -
 R&D Senior Vice Presidentからのメッセージグローバルで活躍する大先輩が語る、若手社員への期待。社会人として、プロのJT社員として大切にしてほしいこととは?
R&D Senior Vice Presidentからのメッセージグローバルで活躍する大先輩が語る、若手社員への期待。社会人として、プロのJT社員として大切にしてほしいこととは? -
 RDS moving on for one team globally場所と文化を越え、メンバーのポテンシャルを引き出し合う「アジャイルな道のり」
RDS moving on for one team globally場所と文化を越え、メンバーのポテンシャルを引き出し合う「アジャイルな道のり」 -
 室内空気環境の評価手法開発低濃度の微量成分の測定を実現するために
室内空気環境の評価手法開発低濃度の微量成分の測定を実現するために -
 ゴールドリーフ葉たばこ原料の開発プロジェクト加熱式たばこに適したたばこ原料
ゴールドリーフ葉たばこ原料の開発プロジェクト加熱式たばこに適したたばこ原料 -
 お仕事対談「調香」という仕事香りの素材を組み合わせて、たばこの香りをより豊かにする「調香」という仕事
お仕事対談「調香」という仕事香りの素材を組み合わせて、たばこの香りをより豊かにする「調香」という仕事 -
 お仕事対談「葉組」という仕事葉たばこをブレンドして味・香りの骨格をつくりあげる「葉組」という仕事
お仕事対談「葉組」という仕事葉たばこをブレンドして味・香りの骨格をつくりあげる「葉組」という仕事 -
 博士号取得者対談多才な人財との協業を楽しみながら、自身のスキルと知見を深化させる。
博士号取得者対談多才な人財との協業を楽しみながら、自身のスキルと知見を深化させる。 -
 たばこを吸わない人対談吸う人も吸わない人も、それぞれの感性や視点を活かして生み出される多様なアイデア
たばこを吸わない人対談吸う人も吸わない人も、それぞれの感性や視点を活かして生み出される多様なアイデア
MEDIA
外部メディア掲載記事の紹介