副社長インタビュー
JT Group Purpose具現化に向けて

「JT Group Purpose」策定に至るまでの長い道のりと、浸透に向けた取り組み。さらに、「心の豊かさ」という提供価値を起点とした活動を行うコーポレートR&D組織「D-LAB」への想いや現状について、二人の副社長にインタビューしました。
JT Group Purpose策定の経緯を教えてください
中野
-
2023年2月にJT Group Purpose(以下、JTG Purpose)を公表しましたが、検討開始から策定に至るまでの道のりは長く、実に3~4年を要しました。JTという会社は本質を追求する姿勢と言いますか、大きな枠組みを形作る際に徹底的に議論する傾向があり、私が2019年の10月に企画担当の役員に就任した後も、主要な役員を集め、ディスカッションを重ねてきました。その中でキーワードとして上がってきたのが、我々のJTG Purposeの中で掲げている「心の豊かさ」です。
JTG Purposeは何のためにつくるのか、何を目指していくのかといった議論もあったのですが、我々がこれまで大切にし、かつ提供してきた価値を全員で自問自答したところ、やはり「心の豊かさ」がキーワードになるとの結論に達したんですね。それ以降は「心の豊かさ」を中心に据えて議論を進めてきました。一方で、グループ全体のJTG Purposeとして「心の豊かさ」という言葉を据えた際に、世界中の従業員が納得し、行動に移せるのかという観点から考え方を整理するために、JTのみならず海外子会社であるJTインターナショナルの幹部なども交えて何度も議論を重ねています。このような過程を経て、最終的に到達したのが「心の豊かさを、もっと。」というJTG Purposeです。
「もっと」が付くのですね?従業員の皆様はJTG Purposeをどう受け止めておられますか?
中野
-
「もっと」という言葉は、個々人が持つ多様な価値観や想いを従来以上に自覚し、気づき、その実現を目指していくという意味における「もっと」というイメージです。
社内における公表は、まずコーポレート部門だけ先行して実施しましたが、「非常に共感できる」という声があった反面、やはり「『心の豊かさ』は多義的な解釈が存在するが、具体的に何を目指すのか?」といった疑問など、さまざまな意見がありました。このためJTG Purpose策定のバックグラウンド、そこに込められた想いなどについて幾度となく従業員に説明し、ディスカッションしました。
また、コーポレート部門で見られた反応は、たばこ事業など他部門でも発生することが予見されましたので、JTG Purpose公表後の昨年一年間で、社長と副社長が分担して国内拠点を網羅的に行脚しました。自らの言葉で伝える努力を重ねることで、一定程度の理解が得られたと実感しています。全員に腹落ちしてもらうにはまだまだ時間がかかると思いますが、愚直に取り組んでいきたいと思います。
今後どのように浸透させ、JTG Purposeの具現化につなげていくのかについて教えてください
嶋吉
-
JTG PurposeはJTグループの存在意義そのものであり、一度策定したからには長期的に存続すべきものと考えています。ただ、従業員が日々の業務においてJTG Purposeを必ずしも意識するわけではありませんので、具体的にオーナーシップ(一人ひとりの主体性)をもって仕事に取り組むための行動指針を策定しています。
もちろんそれで短期的に全員の行動が100%変わるとは考えていません。ただゼロから新たに構築したわけではなく、従来我々が大事にしている「心の豊かさ」といった価値観や行動指針を改めて取り上げているので、全く理解が得られないという心配はしていません。直接的にJTG Purposeを意識する機会は少なくても、そこに根差すフレームワークを踏まえて日々の行動を繰り返していけば、20~30年後にはJTG Purposeが一層身近なものになっていくだろうと考えています。
中野
-
「心の豊かさ」とどう向き合うかという点については、まずは自分自身を見つめ直すということだと考えています。「心の豊かさ」の感じ方は一人ひとり違うはずで、それぞれが独自のものだと思いますが、共通する部分は間違いなくあります。他者の評価を気にすることなく、自分は何が好きで何が嫌いか、また何をしたいのかを自分なりに見極めた上で、他者と重なりあう部分を見出すためにはどうすればいいか、と考えることが重要です。自分自身の考えや感覚がなければ他者とのコミュニケーションや議論が難しくなりますので、対話の際には自分の考えをしっかりと持ち、それを伝えることがスタート地点であると話しています。従業員とのこのような対話は重要ですし、継続して実施する必要があると考えています。
嶋吉
-
JTG Purposeの具現化には、日々の行動や心構えに加えて、各事業の戦略を遂行して経営計画の達成を積み重ねていくことも重要だと考えており、たばこ事業、医薬事業、加工食品事業で、JTG Purposeをそれぞれの事業活動に落とし込み、事業部ごとに事業Purposeを策定しています。
例えばたばこ事業では、「Creating fulfilling moments. Creating a better future.」という事業Purposeを定めています。嗜好品として消費者の心の豊かさに貢献する商品やサービスを通じ、お客様と社会のためのより良い未来の実現に向けて尽力していくということを企図したものです。
医薬事業の事業Purposeは、「科学、技術、人財を大切にし、患者様の健康に貢献します。」です。より事業の具体的な創造価値に即したものとしています。医薬品は法律等でその品質基準が厳しく設定されていると同時に、上市に至るまでの成功確率が低く、かつ成功するプロジェクトであっても開発には相当長い時間がかかります。そのようなビジネスであるからこそ、目的を見失わないこと、最新のサイエンスとテクノロジーを最大限活用しつつ、仲間をはじめとする多くの人たちと協働してはじめて価値創造が可能になるということを肝に銘じつつ、全員一丸となって創薬に励んでいます。
また、加工食品事業は「食事をうれしく、食卓をたのしく。」という事業Purposeを掲げています。単に栄養補給を行うモノ、安全・安心でおいしいモノとしての食品をご提供するに留まらず、期待を超える数々の驚きや新たな出会いといった「うれしい食事」、そして大切な人と一緒に食べる喜びや、食卓を彩る笑顔といった「たのしい食卓」をお客様、社会にお届けしていきたいという想いを込めています。各事業Purposeの実現を目指す取り組みを推進することが、最終的にはJTG Purposeの実現につながるはずです。
また、コーポレート部門ではJTG Purpose実現に向けて、さまざまな検討を組織の垣根を越えて行っています。2024年の2月にJT Group Sustainability Targetsを公表していますが、これは中長期的な視点での検討結果の実例です。現時点では25のターゲットを掲げており、これらのターゲットの達成を通じ、ステークホルダーの皆様への提供価値を拡大させながら、JTG Purposeの具現化につなげていきたいと考えています。
他には、JTG Purpose具現化に直接的につながる取り組みの一つとして、コーポレートR&D組織であるD-LABが「心の豊かさ」を中心概念とした研究や、未来の事業シーズの探索・創出を行っています。
D-LABの生まれた経緯を教えてください
中野
-
まず、我々のメインビジネスは引き続きたばこ事業であって、まだまだRRP(Reduced-Risk Products)*領域も含めて事業成長できると考えています。しかし、長期的なスパンで事業とグループの方向性を見据え、かつたばこ事業における製品の需要動向や規制、税制の変化などを考慮すると、既存事業だけではない別の事業も考えて取り組む必要があります。
*
RRP(Reduced-Risk Products):喫煙に伴う健康リスクを低減させる可能性のある製品
嶋吉
-
たばこという商品はJTG Purposeである「心の豊かさ」を消費者に届ける手法の一つであって、それとは別の形で「心の豊かさ」を届ける商品、サービスを追求していくためにD-LABがあります。その活動は、JTG Purposeの追求そのものでもあります。
中野
-
D-LABが組織になったのは2020年ですが、その7年前に経営企画部内でのプロジェクトとして立ち上げたのが始まりで、足掛け10年は活動をしています。現在は「心の豊かさ」を中心概念とした「心の豊かさという価値の多角的研究」「未来の事業シーズ探索」「未来の事業シーズ創出」の大きく3つの活動を行っており、常に100を数えるプロジェクトが進行しています。
「心の豊かさという価値の多角的研究」においては、大学との共同研究に加え、他企業と協業で「心の豊かさ」という価値の理解を深める活動を実施しています。「未来の事業シーズ探索」においては、スタートアップに投資するファンドへ単独出資しており、当該ファンドは欧米を中心に「心の豊かさ」に親和性がある約200社に投資を実施しています。また「未来の事業シーズ創出」においては、ゼロから事業を立ち上げ、商品・サービスのトライアルを実施したり、複数の製品を販売したりするなど、実際にお客様へ「心の豊かさ」という価値を提供するフェーズに進んでいるプロジェクトも複数あります。
いずれも短中期的なスパンで収益性のあるビジネスにつながることを期待して取り組んでいるわけではなく、さまざまなプロジェクトをより長期的な視点で育成している段階です。
D-LABの取り組みの取捨選択基準は?
中野
-
「心の豊かさ」の解釈を、現段階では広く設定しており、これはJTG Purposeを「心の豊かさを、もっと。」という幅広い言葉で表現したことにも、一部通じます。先ほど触れた通り、個々人で捉え方が違いますし、各地域の文化、時代や社会の変化によっても変わる可能性があります。そのため、まずはこの概念を広義に捉えて、さまざまな取り組みを進めています。
判断に通底するのは「心の豊かさ」に資するかということでしょうか?
中野
-
そうですね。プロダクトであってもサービスであっても、また国や地域にかかわらず、「心の豊かさを人々に提供する」ということがJTグループにとって最も重要な価値となっています。我々は時代や人によって多様に変化していくお客様や社会の「心の豊かさ」に寄り添いながら、現在のJTグループの姿に限定することなく、より発展的なあらゆる企業活動を通じて「心の豊かさ」という価値の提供を実現していきたいと常に考えています。
D-LABの人財、組織についてはいかがでしょうか?
嶋吉
-
現在のD-LABが推進している取り組みに関わる企画が持ち上がった2013年頃、私は人事を担当していましたが、このプロジェクトを実現させるためには人財のセットを見直す必要があると考えていました。JTはエグゼキューション能力が高く、一つのことが決まると、巨大なマシンが動き出すように一気に物事が力強く進展する傾向があります。ただ、まだ見ぬ心の豊かさを実現するためには、意思決定に至るまでに多様な発想や働き方をする人財が必要だと考え、新卒・経験者採用においても視野を広げてさまざまなバックグラウンドを持つ方に集まっていただきました。またそれぞれの能力を最大限に発揮できる働き方や組織の在り方についても検討を重ねてきました。
一方、実際の取り組み自体に関しては、私は社員に任せ、いろいろ口を出さないようにしています。先ほど中野さんがおっしゃったように、間口を広くして取り組んでもらいたいですね。
中野
-
基本的には、彼らのやりたいことをある程度認めて自由な研究を許可しているし、スモールスタートで始める際にもあまり干渉しません。一定規模の資金が必要な段階ではもう少し関与しますが、そこでもかなり自由に対応してもらっています。新しい事業をつくる際には特定のコンセプトを考案し、それを検証し、マーケットに試験的に導入していくという、スタートアップにおけるプロトコルが既に存在しています。これに基づいて進めることで、次のステップを踏むかどうかは一定の範囲において自分たちで決定できます。
まだまだこれからですが、今のところゼロからイチの創出は順調に進んでいます。一方、そのイチから10を、さらに10から100を生み出すには、必要となるケイパビリティが異なります。外部と共同で取り組んでいる経験や知見等を活かして、これからはどうスケールアップやスピードアップしていくのかがテーマになっています。
-

呼吸するロボットクッション「fufuly」
-

ボタニカル素材のポテンシャルを短時間で
高クオリティに引き出す、COLDRAW専用の抽出機器
D-LABでは今後どのように活動を行っていくのでしょうか?
中野
-
現在、呼吸するクッション「fufuly」や、植物本来の味わい・色彩を抽出するノンアルコールドリンクのための新テクノロジー「COLDRAW」など、徐々にこれまでの活動の成果が形として表れてきています。今後はこういった、ステークホルダーの皆様に手に取って「心の豊かさ」を感じていただける取り組みを徐々に増やしていき、長期的にはJTグループの利益成長に貢献できることを目指しています。ただし、こうした取り組みはあくまでも長期的なものであり、短期的なリターンを追求する取り組みではないことをご理解いただきたいです。
嶋吉
-
我々のメインであるたばこビジネス自体はまだ成長できるポテンシャルがあり、お客様のニーズに応えるために加熱式たばこ製品も含め、将来的にさまざまな異なる形態の製品が出てくることを期待しています。そういった検討が、D-LABの活動と有機的にオーバーラップし、協働余地が生まれると、一気に可能性が広がるかもしれないと考えています。
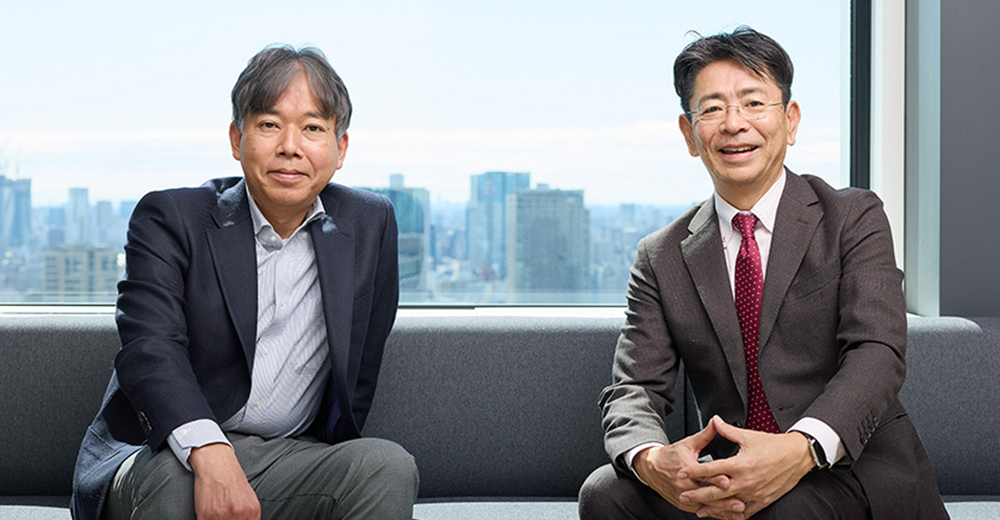
最後にJT Group Purpose実現に向けての意気込みや取り組みをお聞かせください
中野
-
JTG Purposeを具現化するような新しい事業を創出したいという観点からD-LABの話を中心にしましたが、元々たばこビジネス自体が「心の豊かさ」を提供できるものであり、それがあるからこそ現在のJTG Purposeが存在しているという部分もあります。
D-LABでは当然新しい事業に取り組んでいきますが、これは長期的な取り組みであって、実際の事業展開という意味では引き続きたばこビジネスを中心に進めていくこととなります。また、JTG Purposeを実際に社内外で理解していただくための取り組みは短期的なものではなく、時間をかけて続けていく必要があると認識しています。今後も理解や共感を得るための取り組みを検討し、実行していく予定です。
嶋吉
-
事業は財務的なパフォーマンスにつなげていくことが重要ですので、当然それを念頭に置きながらも、同時に自分たちがやりたいかどうかということも大切にしています。我々はJTG Purposeの具現化や、それにつながる現在の事業をやりたいからやっていますし、さらに「心の豊かさ」を提供できるビジネスを始めたい、拡大したい、と思っています。
JTグループの既存の事業、将来の事業を意思を持って展開し、我々が目指す「心の豊かさを、もっと。」を現実のものとしていきたいと考えています。



