CEOメッセージ
-
「心の豊かさを、もっと。」
時代や人により、多様で変化していく「心の豊かさ」の領域を今後も社会から任され、貢献できる存在であり続けるために、JTグループの弛まぬ進化をリードしてまいります。
-
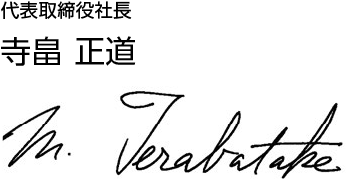
-

2023年の経営環境と業績評価、JT Group Purpose実現に向けて
JTグループにとって2023年はどのような年でしたか?
昨年を振り返る前に、まずは、ウクライナ、スーダン、中東、日本、そして台湾など、世界各地で起きている天災や悲痛な出来事に対して心から哀悼の意を表したいと思います。JTグループは引き続き従業員とその家族の安全を最優先として、各地域への支援を提供していきます。
2023年は、地政学的リスクの顕在化、世界的なインフレーションに伴うサプライチェーンコストの上昇、大幅な為替変動など、事業環境は引き続き厳しく、変化の大きな年でした。
こうした環境下でも、これまでの将来を見据えた継続的な事業投資がベースとなり、全事業において、2023年初めに策定した計画のみならず、2022年度の実績も上回る結果となりました。また、全社ベースでは売上収益から当期利益まで過去最高*1の実績となっています。
JTグループの利益成長の中核かつ牽引役であるたばこ事業について、2023年は国内外のたばこ事業を統合して迎えた2年目でした。今年1月には国内外たばこ事業一本化の最終段階である基幹システム統合が完了し、真の意味でのOne Teamとしてのグローバルでより強固な事業運営が可能になりました。グローバルベースでの資源配分とコラボレーションを通じ、その成果が目に見える形で表れてきています。
Combustiblesでは、プライシング効果が着実に発現するとともに、高いエクイティを持つ我々のブランドから成るバランスの取れたポートフォリオによって力強いシェアモメンタムを維持しています。RRP(Reduced-Risk Products)*2においては、Ploom Xの地理的拡大が順調に進んでおり、2023年末時点の展開市場数は13市場に達しました。また、HTS(heated tobacco sticks)の最大市場である日本では、2023年12月末時点でのカテゴリ内シェアが11.4%に到達するなど、着実な成長を続けています。
また、医薬事業および加工食品事業も増益を達成し、引き続きグループの利益成長を補完しています。
2023年に公表したJT Group Purposeについて申し上げると、例えば、私自身タウンホールミーティングや拠点訪問における社員との対話を通じて、Purposeの浸透、実践の促進を図ってきました。また、社内のみならず、社外のステークホルダーの視点も取り入れた上でPurpose実現に向けた行動を実践できるよう、土台を整えてきたところです。JTグループが貢献していく価値領域や実現したい社会像は社内外の多くの方から共感を得ており、社員からはその実現に向けた力強い意欲を感じています。
そして2024年からはPurposeの実現に向けてさまざまな施策を具現化していくフェーズに入ります。JT Group Purposeを各事業における活動の進化へとつなげていくために、各事業が取り組む方向性を示す各事業の事業Purposeがあります。また、JT Group Purposeの具現化を促進する一環として各事業部やコーポレートの部門ごとに、考え方や行動の規準となる行動指針を策定しました。これは、JT Group Purposeに基づく行動を意識的に進めるための仕組みであり、所属従業員によるワークショップなどを通じて、一人ひとりが主体的に実践するために整えた枠組みです。地道な取り組みを通じたPurposeの着実な浸透、行動指針の実践、各事業戦略の遂行を通じた経営計画の達成を積み重ねていくことによって、Purposeの実現により近づくものと考えています。
*1
売上収益、調整後営業利益、継続事業における営業利益、継続事業における親会社の所有者に帰属する当期利益
*2
RRP(Reduced-Risk Products):喫煙に伴う健康リスクを低減させる可能性のある製品
2023年に開催されたタウンホールミーティングの様子
経営計画2024
経営計画2024について、環境認識と併せて教えてください。
経営環境・事業環境認識
昨今、企業を取り巻く外部環境が一段と複雑化し、企業経営の舵取りは一層困難になっています。その変化は、気候変動や人権問題等のESG関連のみならず、地政学的リスク、技術革新等、多岐にわたります。社会・事業環境が非連続に変化していく中で、社会とその中に存在するJTグループの事業をいかに持続可能なものにしていくか、そして持続的な利益成長にどうつなげていくかが問われているものと思っています。
全社
グループの中長期的な利益成長目標については、引き続き、全社為替一定ベース調整後営業利益(AOP)の年平均mid to high single digit、すなわち1桁台半ばから後半の成長にコミットしてまいります。一方で、今次経営計画期間中、すなわち2024年から2026年にかけての3カ年における全社の為替一定ベースAOPの成長率は、我々の中長期目標の下限となる年平均mid single digit、すなわち1桁台半ばを見込んでいます。2024年は前年同水準を見込む一方で、2025年以降は成長に回帰し、為替一定ベースにおいてその成長率は高まっていく見通しです。
たばこ事業
たばこ事業における事業環境は、総需要の減少・ダウントレーディングの継続に加え、地政学的リスクの顕在化、RRPに対する規制および税制の複雑化や競争の激化、また為替変動リスク等、依然として厳しい状況が見込まれます。
こうした環境の中においても将来にわたって持続的に成長していくため、今後最も市場の成長が見込まれるHTSをCombustiblesに次ぐ第2の成長エンジンとすべく戦略的な投資を加速させていきます。この投資は主にマーケティングにかかるものであり、新たなHTSデバイスの投入や現行のPloom Xの地理的拡大および既存市場でのシェア獲得に向けたものが大部分となる予定です。継続的な投資を通じた数量成長により、RRP関連売上収益は2026年には2023年比で約2.5倍になることを見込んでおり、加えて、Combustiblesにおけるシェア成長、そしてプライシングをドライバーとして、力強いトップライン成長を目指します。2024年はRRPへの投資の増加やインフレに伴うサプライチェーンコストの上昇によって、このトップラインの伸長が相殺されますが、これらの影響は徐々に緩やかになり、2024年から2026年の年平均で見れば、たばこ事業の為替一定AOP成長率はmid single digitとなる見込みです。
また、RRPビジネスに関して付け加えさせていただくと、以前から申し上げている2028年のRRP中期展望、すなわち、「HTSセグメントにおける10%台半ばのカテゴリシェア獲得」および「RRPビジネスの黒字化」については順調に進捗していることを確認しています。投資を増加させる一方で、トップラインの成長、またこれに伴う生産性の向上により、今般の経営計画期間中後半にかけて、RRPビジネスの損益は改善フェーズに入ってくることを見込んでいます。
医薬事業
医薬事業については、各国財政逼迫に伴う医療費削減により、引き続き薬価引き下げの大きな圧力が存在しており、また、海外ロイヤリティ収入の減少傾向が継続するなど、事業環境は厳しいものと認識しています。そうした中、次世代戦略品の研究開発と各製品の価値最大化により、引き続きグループへの利益貢献を目指します。2024年からの3カ年においては、期間中、利益水準を維持する見通しです。
医薬事業においては、上場子会社として保有する鳥居薬品株式会社とともに一体的なバリューチェーンを構築しております。当社が研究開発を行う一方で、同社が製造・販売およびプロモーション活動を担っており、事業価値拡大に向け、効率的な協業体制を確立しています。上場に伴うコストはあるものの、同社が上場企業として自律的に企業経営を行っていくことは、優秀な人的資本の確保およびモチベーション向上や信用の獲得等に資するとともに、同社独自の事業活動によるさらなる競争力強化や成長機会の確保にもつながることから、同社の企業価値向上だけでなく、当社が目指すグループ全体の中長期にわたる持続的な利益成長と企業価値の向上に寄与するものと考えています。
加工食品事業
加工食品事業については、国内ではライフスタイルの変化に伴う簡便化ニーズの高まり等により市場規模は拡大傾向です。海外では、人口増加、所得水準の向上、日本食文化の世界的な普及により、事業機会が増加しています。高付加価値な商品群への資源配分強化などを通じて、トップライン成長を中心とした持続的な利益成長を目指していきます。2024年からの3カ年においては、期間中mid single digitの利益成長を見込んでいます。
経営資源配分方針
経営資源配分方針においては、「4Sモデル」およびJT Group Purposeに基づき、持続的利益成長につながる事業投資、とりわけたばこ事業への投資を最優先していくことに変更はありません。株主還元についても、中長期的な当期利益の成長を実現し、配当性向75%を目安*として、株主還元の向上を目指していきます。
なお、配当金については、2023年の財務実績および株主還元方針を踏まえ、期末の1株当たり配当金を期首にお示しした予想値から6円増配した100円とし、中間配当金94円を含めた2023年の1株当たり年間配当金は、過去最高となる194円としました。
*
±5% 程度の範囲内で判断
JT Group Purpose策定の意義
JT Group Purposeの策定の意義を改めて教えてください。
JTグループが将来にわたり、各ステークホルダーから必要とされる存在であり続けるために、経営理念である「4Sモデル」を羅針盤にしながら、体現すべき“存在意義”を明確化する必要があるという課題認識がありました。
JT Group Purposeは、過去から「JTグループがお客様にどのような価値を提供してきたのか」という観点、「今」という視点、「例えば2050年といった超長期の将来の姿」を見据え、将来からバックキャスティングした時に、JTグループが「未来社会においてどんな存在でありたいのか」、「未来社会からどんな存在であれば受け入れられるのか」、「将来的にどんな未来社会に貢献ができるのだろうか」ということを明確にすべく議論を重ね、策定した経緯があります。そしてJTグループの存在意義を「心の豊かさを、もっと。」というキーワードに収斂させました。
製品やサービスを通じて「心の豊かさ」を感じる瞬間に常に寄り添うとともに、その瞬間を創り上げていくことは、我々がこれまでも取り組んできたことです。そして、それを追求し続け、未来社会においてもJTグループの事業体としての持続可能性を目指すことで、社会もJTグループも両方が持続可能となるという視点を取り入れているメッセージにしています。
「心の豊かさを、もっと。」は、目まぐるしい勢いで変化する社会、不確実性の高い経営環境において、我々が「人」、そしてその「心」に寄り添っていく存在でありたいというメッセージでもあります。既存のたばこ、医薬および加工食品事業が今まで提供してきた商品・サービスもそうですが、これからは現在のJTグループの姿に限定せず、より発展的なあらゆる企業活動を通じて「心の豊かさ」という提供価値を実現していきたいと考えています。
これに向けて、「心の豊かさ」という価値を中心概念とした多角的研究や、未来の事業シーズの探索・創出を長期的視点で継続するために、コーポレートR&D組織である「D-LAB」を設置しています。例えば、心に関するウェルネス、呼吸、睡眠、香りや食であったり、五感に訴えるようなものであったり、そうしたものが我々のこれからの事業領域としてターゲットに入ってくるのではないかと考えています。D-LABの活動は、JTグループの利益成長への貢献も目指しており、トライ・アンド・エラーを繰り返しながら約100件のプロジェクトを進めています。既にクラウドファンディングを通じて販売を行っている製品や、海外のイノベーションアワードを受賞するテクノロジー等も出てきており、徐々にではありますが活動の成果が表れ始めています。
このように、JT Group PurposeはJTグループが目指すべき方向性を明確に定めたいわば北極星であり、これに向かうための羅針盤としての「4Sモデル」の追求を通じて、我々のあらゆる活動を進化させ、超長期にわたる期間においても企業価値の継続的な向上を実現したいと考えています。
サステナビリティ経営の進化
Purpose具現化に向けて今般見直されたサステナビリティ戦略について教えてください。
我々は、「自然や社会が持続可能であってはじめて、人の暮らしや企業の活動も持続可能になる」という考えのもと、JT Group Purposeの具現化を通じて持続可能な自然や社会づくりに貢献していくために、2023年5月、サステナビリティ経営の根幹となる「JT Group Materiality」を改定し、JTグループとして優先的に取り組むべき重要事項として5つの課題を特定しました。
加えて、改定したマテリアリティを踏まえ、JTグループとしての具体的な目標および取り組みについても検討を進めてきました。そして、この度、全25項目からなる「JT Group Sustainability Targets」を策定しました。これらのターゲットの実現は、当社Purposeの具現化につながるものと考えています。
JT Group Sustainability Targetsでは、マテリアリティとのつながりを重視し、これまでの取り組みを踏襲しつつ、JTグループとして、具体的な目標および取り組みを設定しました。例えば、「自然との共生」を推進するために、生物多様性の保全も見据え、まずはJTグループの事業の生態系への影響を包括的に把握していきます。
また、「人財への投資と成長機会の提供」を考えるにあたっては、JTグループにおける人的資本の明確化に加え、その拡充に向けて注力するさまざまなターゲットを設定しました。具体的には、人的資本を、企業活動を支える「人財」、活動の判断基準・行動様式となる「組織風土」、人財と組織風土を融合させるための「オーナーシップ(一人ひとりの主体性)」と定義しました。さらにターゲット設定においては、人的資本の状態だけでなく、それらに紐づく活動(人事施策)の進捗や結果を把握するための指標を設定しています。これらのモニタリングを通じて、今後も人的資本の着実な拡充へ取り組んでいきます。
各項目に紐づく目標や取り組みの詳細については、JTグループのサステナビリティ戦略をご参照ください。
JT Group Purposeを起点とした新サステナビリティ戦略に通底するのは、「人の暮らしや社会、企業の活動、あらゆる人の営みは、生態系を紡いでいく一部であり、未来づくりを担う企業として、JTグループは主体的に社会課題の解決に取り組んでいく」という考えです。
この新サステナビリティ戦略の策定・運用には、CEOである私はもちろん、取締役会が関与する体制をとっており、今般策定したJT Group Sustainability Targetsについても、その運用の中で定期的に点検し、進化させていきます。
JT Group Materiality:5つの課題
-
自然との共生
-
お客様の期待を超える価値創造
-
人材への投資と成長機会の提供
-
責任あるサプライチェーンマネジメント
-
良質な
ガバナンス
ステークホルダーの皆様へのメッセージ
ステークホルダーの皆様へのメッセージをお願いします。

我々JTグループは、時代や人により、多様で変化していく「心の豊かさ」の領域を今後も社会から任され、貢献できる存在であり続けたいと考えています。そのためには、JT Group Purposeの具現化に向けた取り組みを進めていく必要があります。行動指針やJT Group Sustainability Targetsの策定、D-LABにおける取り組みなど、枠組みは徐々にできつつあります。この枠組みの中でのその実効性を最大化していくために、私自身、従業員や社外のステークホルダーの皆様との対話を通じて、Purposeのさらなる浸透と、その実現に向けての具体的な行動の実践を促進してまいります。
繰り返しになりますが、Purposeの実現に向けた羅針盤となるのは、やはり我々の経営理念である「4Sモデル」の追求、「お客様を中心として、株主、従業員、社会の4者に対する責任を高い次元でバランスよく果たし、4者の満足度を高めていく」という考え方に他なりません。我々の強みである「強固な財務基盤」「卓越したブランド力」「人財の多様性」を源泉として、この「4Sモデル」を愚直に追求していくことが、中長期にわたる持続的な利益成長、企業価値の継続的な向上、そしてPurposeの実現につながるものと確信しています。
JTグループがこれまでも提供してきた「心の豊かさ」という価値。人々にとってのこの価値は今後も変わり続けていくことでしょう。その中にあっても将来にわたって我々がずっと「心の豊かさ」という価値を提供できるよう絶えず進化していくために、引き続き長期的な視野をもって今私がすべきことやできることを考え全力で取り組んでまいります。








