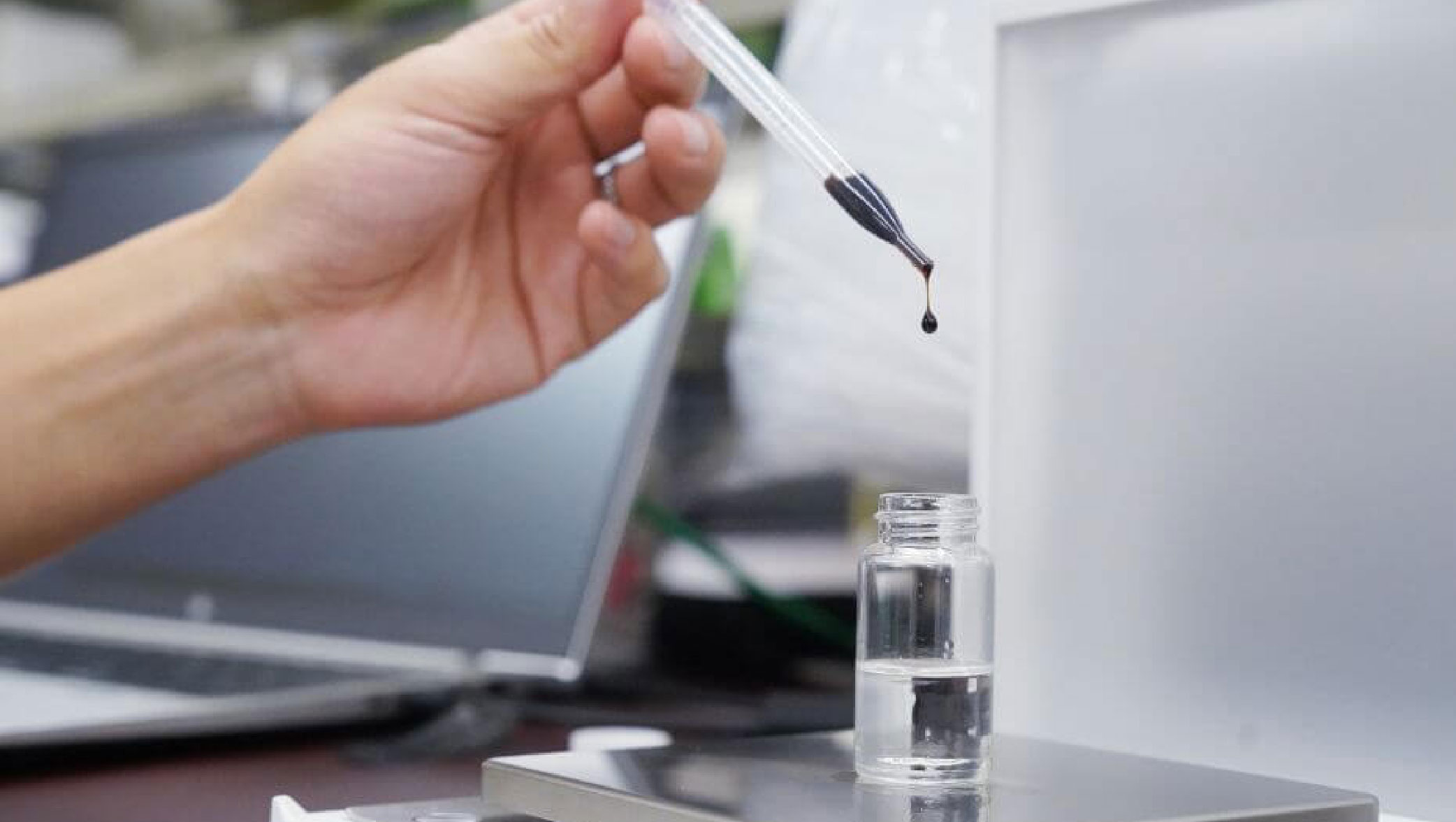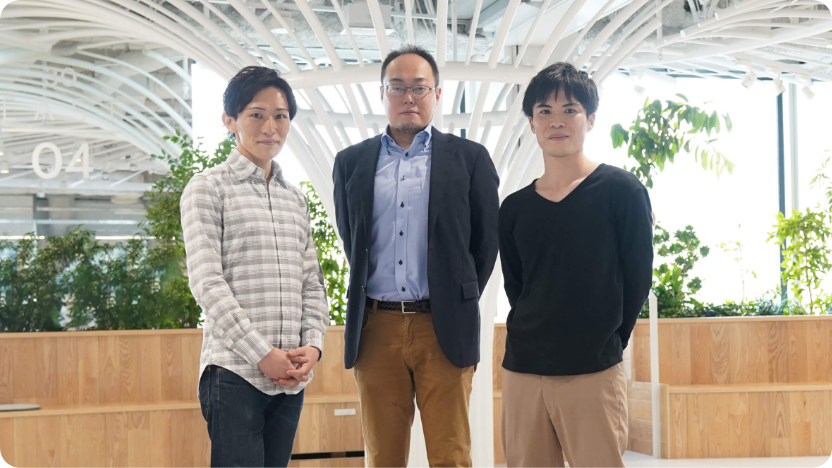お仕事対談
スペシャルコンテンツ


香りの素材を組み合わせて、
たばこの香りをより豊かにする
「調香」という仕事
「調香」は、香素と呼ばれる香りの素材を組み合わせて香料をつくり、たばこ製品に銘柄ごとのキャラクターを彩っていく仕事。その
さじ加減ひとつで、味や香りに大きな影響を
与えるだけに、フレーバリストたちは慎重
に、かつ大胆に、レシピづくりに取り組んで
います。
MEMBER

技術開発
室本 亮介
RYOSUKE MUROMOTO
紙巻たばこ用の香料開発とメンテナンスを担当。

技術開発
澁谷 哲朗
TETSURO SHIBUYA
加熱式たばこ用スティックの香料開発を担当。

技術開発
朴 夏林
HALIM PARK
加熱式たばこ用スティックの香料開発を担当。
TOPICS
-
「調香」とはどんな仕事ですか?
仕事の内容と流れを教えてください。 -
「調香」の仕事のおもしろさや
やりがいは、
どんなときに感じますか? -
「調香」の仕事で大事にしていることは
何ですか?