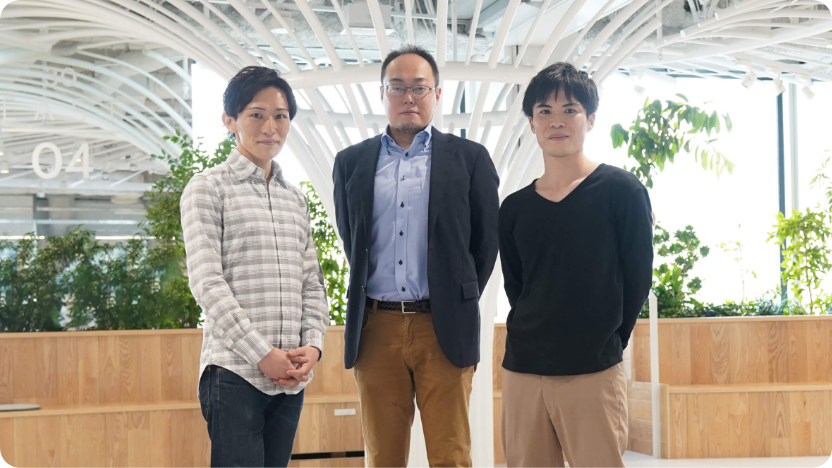お仕事対談
スペシャルコンテンツ


葉たばこをブレンドして
味・香りの骨格をつくりあげる
「葉組」という仕事
たばこ製品には数種類の葉たばこがブレンドされています。試行錯誤しながら、その葉たばこのブレンドをつくりあげていくのが「葉組」という仕事。葉たばこのブレンドは味と香りの中核を成すため、担当者は職人的な感性を駆使しながら、取り組んでいます。
MEMBER

技術開発
永山 萌夏
MOEKA NAGAYAMA
RRP※の新製品開発の葉組とメンテナンスを担当。
Reduced-Risk Products:喫煙に伴う健康へのリスクを低減させる可能性のある製品

技術開発
佐藤 勲
ISAO SATO
紙巻たばこの新製品開発の葉組とメンテナンスを担当。

技術開発
平井 俊史
TOSHIFUMI HIRAI
紙巻たばこのメンテナンスと葉たばこの使用計画策定を担当。
TOPICS
-
「葉組」とはどんな仕事ですか?
仕事の内容と流れを教えてください。 -
「葉組」の仕事のおもしろさややりがいは、
どんなときに感じますか? -
今後、「葉組」の仕事で
チャレンジしたいことは何ですか?