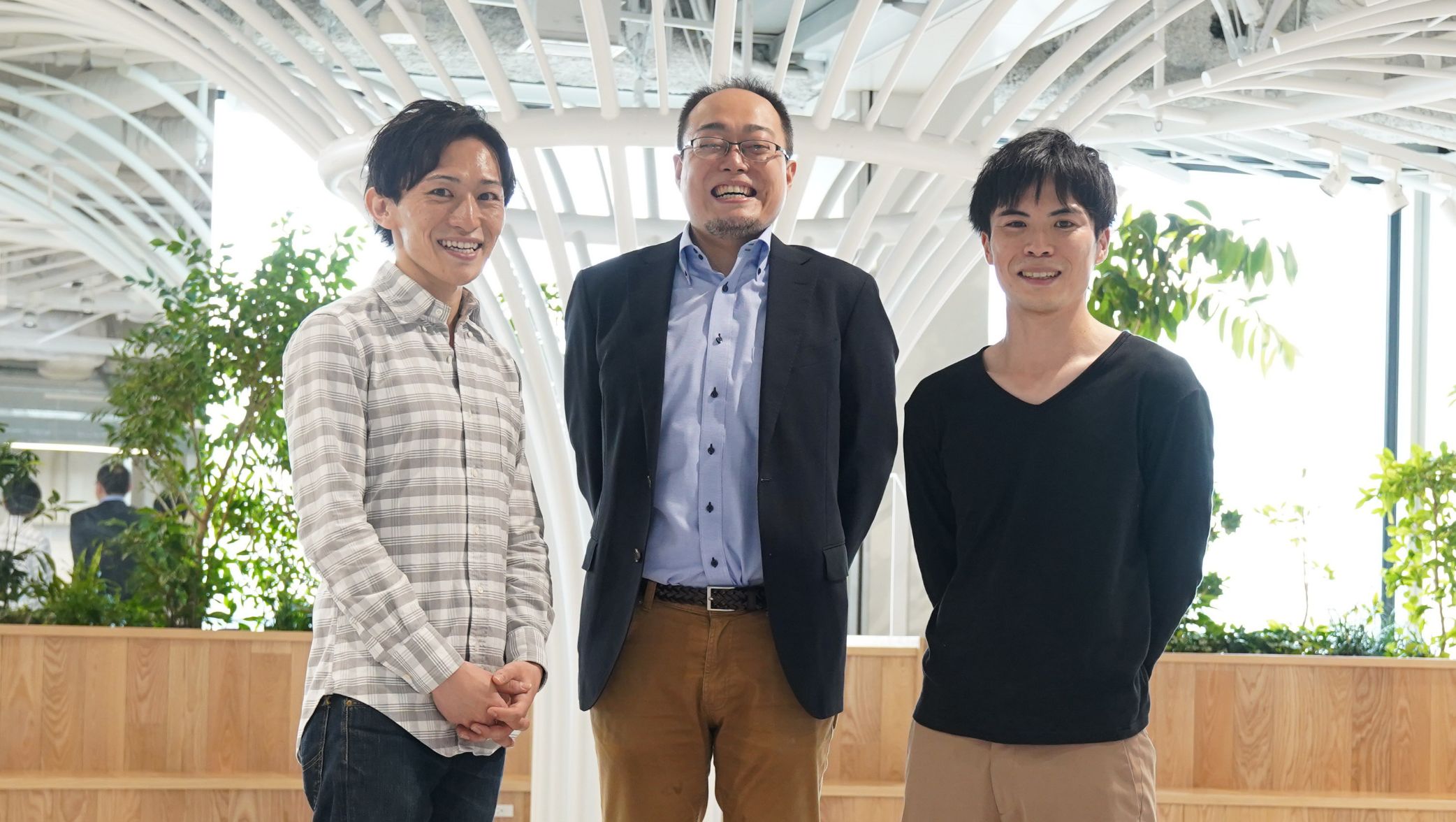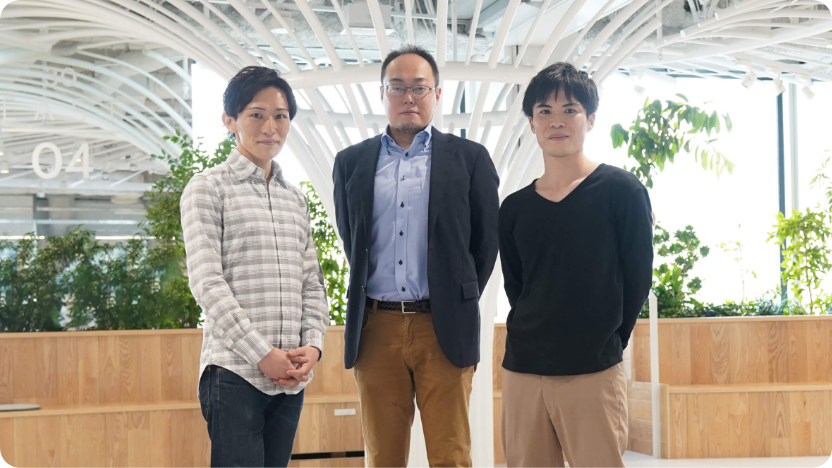博士号取得者 対談
スペシャルコンテンツ

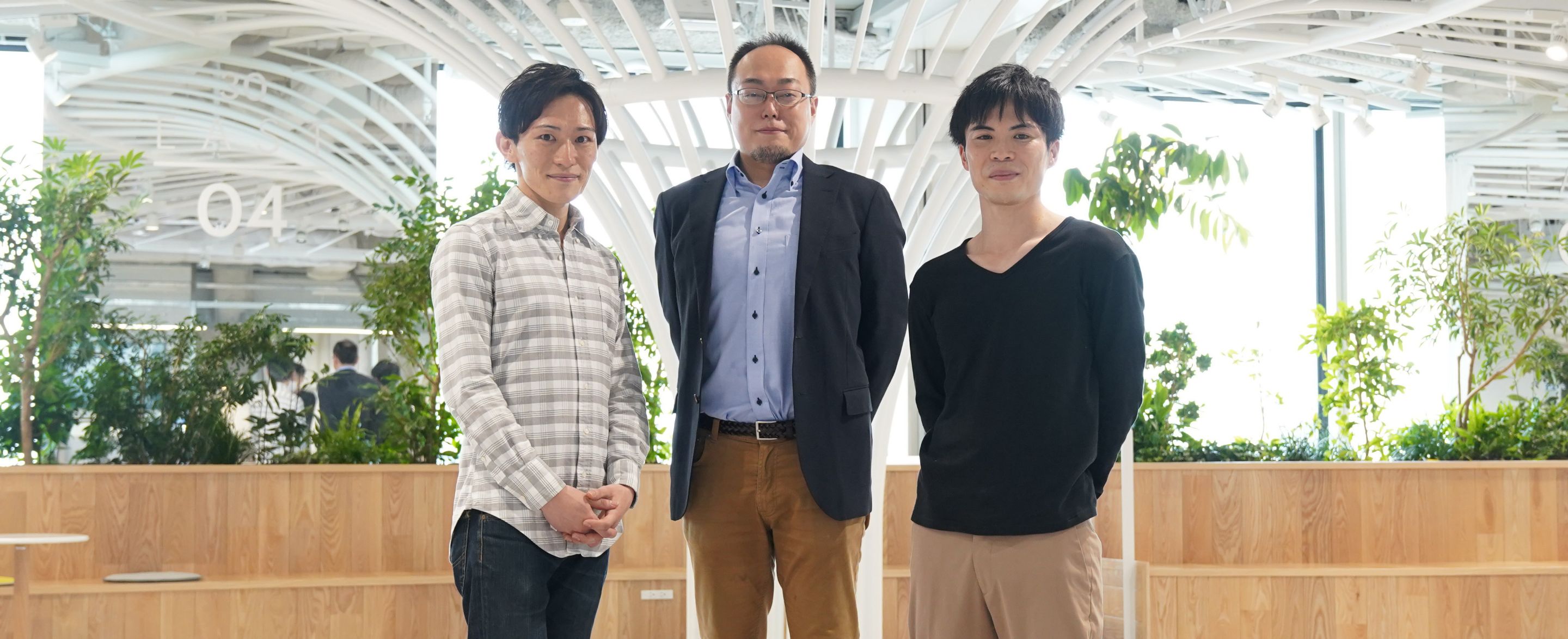
多才な人財との協業を楽しみながら、
自身のスキルと知見を深化させる。
R&D グループには博士号取得後に入社した者、仕事をしながら博士号を終了したものなど、博士号取得者が多く在籍しています。「入社後に博士号を取得することはできるのか?」「博士課程で学んだことをどう仕事で生かしているのか?」基礎研究や製品開発に従事している3名に語ってもらいました。
MEMBER

基礎研究
石川 晋吉
SHINKICHI ISHIKAWA
たばこ煙が生物に与える影響について研究。2010年に新卒入社。2018年に日本毒性学会認定トキシコロジストを取得。2020年に博士号を取得。

技術開発
工藤 健一
KENICHI KUDO
たばこ製品に使用する香料の素材の開発・管理を担当。
博士号取得後、2010年に新卒入社。

技術開発
登 貴信
TAKANOBU NOBORI
加熱式たばこ開発における化学分析を担当。
博士号を取得後、2018年に新卒入社。
TOPICS
- 博士号を取得した理由を教えてください。
-
博士課程での経験や得られた知見は、
現在どのように活用していますか? - 研究のサポート体制はいかがでしょうか?
-
JTグループで今後
何を実現していきたいと考えていますか?