キャリア採用トップ 職種一覧 法務系スタッフ(総合職) 法務系スタッフに求められる素養/キャリアの考え方
法務系スタッフに求められる素養
JTでは、JTグループの多様な力を結集するにあたり、多様な文化や環境下の業務に対応できるよう、論理的思考に裏打ちされた戦略的かつ付加価値のある提言をタイムリーに行うことのできる人財の育成を目指しています。
そのためには、専門知識のみならず、相手のニーズを的確に捉えるために情報収集し整理する、問題の本質を明らかにするためにとことん考える、責任感を持って最後まで取組む、健全な倫理観を持つなど、企業人としての大切な素養が必要となります。
法律を学ぶことは、これらの素養を身につけるために有効な手段の一つですが、やはり土台となるのは法的知識だけでなく、「見る・聞く・知る」、「考える」、「答える・応える」、「伝える」といったシンプルで地道な作業です。以下、法務部門の業務を例に説明しますが、これらは、全ての仕事において同様に求められるものです。
法務部門人財に期待されるもの
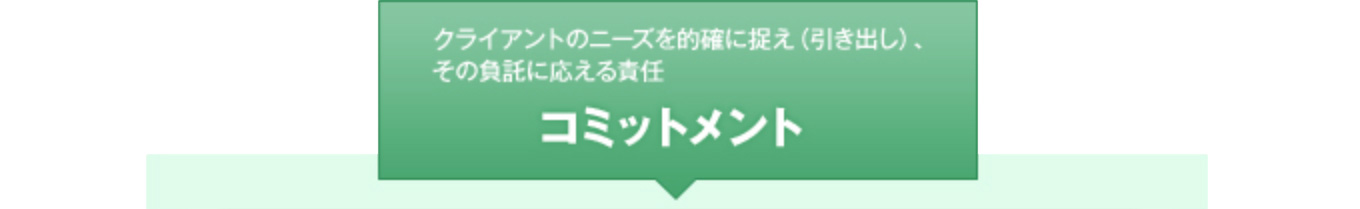
法務系スタッフのキャリアの考え方
自らの殻に閉じこもることなく、あらゆる事象・分野・領域・世界に対する好奇心を持ち、法曹・企業内法務という枠に捉われずに可能性を広げたい・チャレンジしたいと考えている方のご応募をお待ちしております。
JTにおける法務系スタッフとそのキャリアの考え方

法務系スタッフ採用募集要項の必要条件を満たす皆さんの強みは、論理的思考能力の鍛錬・幅広い分野の勉強経験という固有のバックグラウンドと、そこから得たリーガルマインドだと考えています。
入社後はその強みを活かして、多角的視点で本質を捉え、課題を抽出し、解決するビジネススキルやマインドを身に着け、発揮していただくことを期待します(リーガルマインドに加えてこのようなビジネススキル・マインドを有する総合職社員のことをJTでは“法務系スタッフ”と表現しています)。そして法務系スタッフとしての経験を軸として、どの部門でも活躍できるビジネスパーソンとして成長し、活躍の場を広げていっていただきたいと考えております。
また、法務系スタッフの能力は、必ずしも司法試験の合否や法曹資格の有無によって一律に判断できるものではないと考えています。採用にあたり司法試験の合否を一切問わないこと、インハウスローヤーでの採用ではないこと、また採用後資格手当等の措置をとっていないことはこの考え方に基づきます。
